詐欺サイトの見分け方と通報方法【初心者でもできる安全対策】
インターネットを利用していると「このサイト、なんだか怪しい…」と感じることがあります。詐欺サイトに誤ってアクセスしてしまうと、個人情報やお金を失うリスクがあるため、初心者の方でもすぐにできる対応方法をまとめました。
怪しいサイトの特徴
- 公式サイトに似せたドメイン(例:似た文字の置き換え;l(エル)を1にしたり、outletといったセールに関する単語を用いる)
- 不自然な日本語や翻訳文が多い
- ブランド品が極端に安く売られている
- 支払い方法がクレジットカードのみなど限定的
- SSL証明(https://)がなく「保護されていない通信」と表示される
まずやるべきこと
- 個人情報(名前・住所・電話番号・クレジットカード情報)は絶対に入力しない
- URLをよく確認し、公式サイトと照合する
- 少しでも怪しいと感じたらアクセスを中止する
Googleに通報する
怪しいサイトを発見したら、Googleに通報して他の人の被害を防ぎましょう。
➡️ 通報フォームはこちら: Google セーフブラウジング レポート
セキュリティソフトで確認
セキュリティソフトを導入していれば、怪しいURLを入力して安全性を確認できます。多くの場合、危険なサイトは自動でブロックされます。
間違えてアクセスした場合の対応
- サイトを見ただけでは基本的に被害はないので落ち着く
- 怪しいファイルをダウンロードしてしまった場合はすぐにセキュリティスキャン
- クレジットカード情報を入力してしまったら速やかにカード会社へ連絡
まとめ
怪しいサイトでは「入力しない・信用しない・拡散しない」が鉄則です。もし不審なURLを見つけたら、Googleの通報ページへ報告しましょう。
👉 初心者の方は「少しでも怪しい」と感じたら行動を止めることが一番の防御策です。

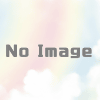
 https://www.oji-be-free.com/2025/3855/
https://www.oji-be-free.com/2025/3855/
